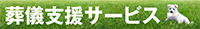妊娠、出産は体への負担度合いが男性と女性で大きく異なる為、利用できる規定や制度も大きく異なってきます。以下の2パターンに分けて説明していきます。




出産した場合、会社と組合の両方から出産祝金がもらえます。
会社の規定では正社員、勤務地限定社員、勤続6ヵ月以上のクルー社員の方が対象となっていますが、組合からの祝金は全組合員が対象となっています。

出産を証明できる書類(出生証明書、母子手帳など)を用意し、所属長を経由して申請。
・申請方法
会社への申請
ダイナムネットからワークフローにて起票
≪ワークフロー⇒新規イベント⇒出産⇒本人申請≫
ユニオンへの申請
ユニオンへの申請は、申請書と出産を照明できる書類を併せてFaxにてお願いします。
≪ダイナムネット⇒社内文書⇒ユニオン⇒組織慶弔見舞金⇒組織慶弔見舞金申請書≫
出産して子供が増えた場合、家族手当が支給されるようになります。
くわしくは結婚編でご覧下さい。
組合からの記念品は今まではアルバムとなっていましたが、時代の変化と共に写真用のアルバムはあまり必要性が無くなってきたとのご意見を頂いていましたので、2008年度からはアルバムからカタログギフトに変更しました。
配偶者が出産したときにもらえる特別休暇が出産休暇となります。
いずれの社員区分でも3日間となっていますが、勤務地限定社員と正社員の方は有給となります。
なお、1日単位で分割して取得することも可能です。
奥さんの出産時の入退院の付き添い、出産の立会いなどに利用することができます。

・申請方法:ダイナムネットからワークフローにて起票
≪ワークフロー⇒新規申請⇒就業関連⇒休暇申請書⇒本人申請≫
妊産婦(妊娠中、産後1年を経過せず復帰された方)である従業員が、妊娠または出産に伴う症状により、就業が困難として申出た場合は必要な日数の休暇を取ることができます。
なお、つわり以外の症状でも利用が可能な制度となっています。
※つわり等休暇に限らず、時間短縮も社員区分に関わらず無給となります。
妊娠中である従業員が、保険指導または健康診査を受けるための通院にかかる休暇を申請することができます。

妊娠中の女性社員は、他の軽易な業務への配置転換を請求することができます。
請求をしたのち、所属長と面談をした上でカウンターや事務作業に変更などの軽易業務に変更することができます。
妊娠している従業員が申出た場合に、残業しないという申請ができます。
1週間について40時間、1日について8時間を越えて就業しないという申出です。
同様に休日勤務、深夜労働についてもしないという申請が可能です。
妊娠している従業員が申出た場合に、15分単位で勤務時間を短縮する申請ができます。
短縮できる就業時間は2時間までとなります。通勤ラッシュを避けて出勤する等に利用することができます。
妊娠している従業員が申出た場合に、15分単位で休憩時間を延長する申請ができます。
延長できる休憩時間は1時間までとなります。妊娠に伴う症状により、少し休憩したい場合等に利用することができます。
妊産婦である従業員が申出た場合は以下の措置を請求することができます。ただし本部、統括勤務者と店舗勤務者では措置に違いがありますのでご注意下さい。
○本部、統括勤務者
・15分単位で就業時間の短縮ができます
・半日有給休暇を取得することができます(この場合の回数は無制限)
○店舗勤務者
・15分単位で就業時間の短縮ができます
・勤務シフト表に定められた勤務日や就業時間の変更ができます
このあたりも非常に分かりにくくなっていますので解説します。
上記で出てきたものを簡単に表現すると、
「⑤つわり等休暇」は「つわり等で具合の悪いときは休暇が取れますよ」 という規定であり、「⑥妊娠中・出産後の健康管理のための休暇」は「保健指導や健康診査を受けるときは休暇がとれますよ」 という規定です。
しかし休暇だけではなく、就業時間の短縮や、半日有給休暇なども必要ということで、こういった「⑪妊娠・出産に伴う症状に対する措置」の規定が付け加えられているということです。
なお、上記の半休取得は通常の半休取得日数(年間6回まで)にはカウントされません。
⑤〜⑪は全て「マタニティー制度に係る申出書」にて申請ができます。
≪社内文書⇒申請・届出⇒人事労務⇒マタニティー制度≫ 以下の3ファイル
・マタニティー制度について …解説書
・マタニティー制度に係る申出書 …これに記入して人事部へFAX
・母性健康管理指導事項連絡カード …2ページ目の最後に署名して病院に持参
マタニティー制度に係る申出書(以下マタニティー申出書)の中には、母性健康管理指導事項連絡カード(以下母健カード)が必要になるものがあります。
(⑤ ⑨ ⑩ ⑪)がそれに該当します。マタニティー申出書をFAXする前に、病院で記載してもらっておいて下さい。
〔産前休暇〕
妊婦である従業員が申出た場合に、出産予定日の6週間前(※1)から休暇を取得できます。
(※1):多胎妊娠(双子以上)の場合は14週前
〔産後休暇〕
出産日の翌日から8週間は、就業することができません。労基法で定められています。
ただし、産後6週間を経過後、本人が請求し医師が認めた場合には就業が可能です。
・申請方法:ダイナムネットからワークフローにて起票
≪ワークフロー⇒新規申請⇒就業関連⇒休暇申請書⇒本人申請≫
産前産後休暇は無給休暇となりますので、その間の給与はゼロとなるどころか、通常引かれている控除金の分がある為、給与がマイナスとなってしまいます。⑭で勉強する出産手当金で健康保険から給与の3分の2は補填されますが、その振込みはしばらく先となってしまう為、本人以外に収入が無い家庭の場合、あらかじめ貯金をしておかないとお金が不足する事になってしまいます。
金額はそれぞれ異なりますが、自分にしか収入が無い場合、給与の3ヶ月分くらいはあった方が良いでしょう。
健康保険からもらえるお金となります。金額は子ども1人につき39万円(平成21年1月以降、産科医療補償制度に加入している医療機関等において出産したときは1人につき42万円)の支給となります。もし、死産や流産の場合でも、妊娠85日以上であれば支給されます。
(申請からおよそ2か月後に振り込まれます)
申請書の起票は以下の通りですが、病院で証明してもらう欄がありますので、入院時には忘れずに持っていきましょう。証明をしてもらったら、ダイナム情報処理に送付して下さい。
・申請方法:ダイナムネットからワークフローにて起票
≪ワークフロー⇒新規イベント⇒出産⇒本人申請≫
あらかじめ手続きをしておけば、出産育児一時金の39万円を直接病院へ振り込んでもらい、持ち出しはその差額だけを支払うという形も可能となっています。
【申請方法】
出産予定日の1か月前から受付てもらえますので、あらかじめ加入している健康保険組合に問い合わせをして事前申請用紙を郵送してもらい、病院から証明印をもらって健康保険組合に郵送して下さい。
健康保険の被保険者(本人出産の場合)が、出産のために仕事を休んでいる産休(産前42日、産後56日)期間の給料を保証してくれる制度です。
もらえるお金は標準報酬日額(1日あたりの賃金)の3分の2に、98日間分を掛けた金額となります。もし、予定日より早く生まれたら、その日数分減ってしまいますが、反対に予定日よりも遅れると、42日よりも産前分が増えることになります。
こちらも⑬と同様に印字(A3サイズ)しておき、病院への入院時に持って行きましょう。
証明してもらったら、同様にダイナム情報処理に送付して下さい。
産後56日から更に1〜2ヶ月後にまとめて口座に振り込みされます。
・申請方法:ダイナムネットからワークフローにて起票
≪ワークフロー⇒新規イベント⇒出産⇒本人申請≫
| 制度 | 規定名 | 正社員 | キャスト社員 | クルー社員 |
|---|---|---|---|---|
| (1)出産祝金 | 慶弔見舞金規定 | 9条 | 9条 | – |
| (2)家族手当 | 給与規定 | 19条 | 13条 | – |
| (3)組合から出産祝金+記念品 | 組合慶弔規定 | 3条 | 3条 | 3条 |
| (4)出産休暇 | 就業規則 | 42条1項(2) | 33条2項(2) | 33条1項(2) |
| (5)つわり等休暇 | 就業規則 | 42条2項(7) | 33条2項(7) | 33条1項(12) |
| (6)妊娠中・出産後の健康管理のための休暇(通院休暇) | 就業規則 | 42条2項(8) | 33条2項(8) | 33条1項(13) |
| (7)軽易業務への配置転換 | 就業規則 | 42条3項 | 34条3項 | 34条3項 |
| (8)時間外労働・休日労働・深夜業の制限 | 就業規則 | 43条4項 | 34条4項 | 34条4項 |
| (9)勤務時間の短縮 | 就業規則 | 43条5項 | 34条5項 | 34条5項 |
| (10)休憩時間の延長 | 就業規則 | 43条6項 | 34条6項 | 34条6項 |
| (11)妊娠・出産に伴う症状に対する措置 | 就業規則 | 43条7項8項 | 34条7項・8項 | 34条7項・8項 |
| (12)産前産後休暇 | 就業規則 | 42条2項(2) | 33条2項(2) | 33条1項(7) |