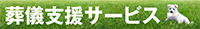男女を問わず、生後満1歳に満たない子と同居し養育する従業員は子が1歳に達するまでの(条件が満たされる場合は最長1歳2カ月まで)希望する期間、子どもを養育するために休業することができます。(無給休暇)
育児休業は男女問わず取得できますが、養育を行なう予定であったものが以下に該当した場合は取得する事ができません。
1.死亡したとき
2.傷病または精神上もしくは身体上の障害により申出に係る子の養育をすることができなくなったとき
3.6週間(※2)以内に出産する予定であるとき
4.産後8週間以内であるとき
5.申出に係る子と同居しなくなったとき
(※1):1週間の所定労働日数が2日以下の者および育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業その他の休業により就業していない者を含む
(※2):多胎妊娠の場合にあっては、14週間
また、申請する従業員が次に該当する場合も育児休業が取れません。
・勤続1年未満の者
・申し出の日から1年以内に退職することが明らかな者
育児休業の期間は、以下のケースにおいては1年6か月を上限として延長することが可能です。
・保育所の申込を行なっているが、当面その実施が行なわれない場合
このように育児休業は取得する際の制限が細かく決められていますので、確認が必要です。
母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヶ月に達するまで延長されます。
パパ・ママ育休プラスの取得用件
1.配偶者の一方が先に育児休業を取得している
2.もう一方の配偶者は、子の1歳の誕生日までに育児休業を開始する。
3.育児休業期間は、父親は最長1年、母親は産後休業とあわせて最長1年

配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能です。

配偶者が専業主婦(夫)家庭の夫(妻)であっても育児休業取得が可能です。

・申請方法:ダイナムネットからワークフローにて起票
≪ワークフロー⇒新規申請⇒就業関連⇒育児休業申出書⇒本人申請≫
※育児休業の申請は、育児休業を開始しようとする日の1か月前までに、子の妊娠、出生または養子縁組の事実を証明する書類を添付して届けなくてはなりません。
小学校就学前までの子を養育する従業員は、1日2時間以内の所定勤務時間の短縮措置を受けることができます。この制度も男女問わず利用する事が可能です。(2011.4.21改定;改定前は3歳未満まで)
・申請方法:ダイナムネットからワークフローにて起票
≪ワークフロー⇒新規申請⇒就業関連⇒短時間勤務申出書⇒本人申請≫
【育児のための深夜業の制限】
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が申出た場合は、事業の正常な運営に支障があるときを除き、午後10時から午前5時までの間の労働を免除されます。
【育児のための時間外労働の制限】
上記の深夜業の制限と同様に、時間外労働の制限もすることができます。1か月につき24時間、1年につき150時間を上限とすることが可能です。
ただし、以下のどれかに該当する従業員は請求することができません。
〔深夜業、時間外労働の制限を請求することができない者〕
・勤続1年未満の者
・請求に係る子の16歳以上の同居の親族が、次の1〜4全てに該当する者
1.深夜において就業していない者(※1)
2.傷病または精神上もしくは身体上の障害により子の保育をすることができない者でないこと
3.6週間以内(※2)に出産する予定でない者
4.産後8週間以内でない者
・ 1週間の所定労働時間日数が2日以下の者
※1:深夜における就業が1か月について3日以下の者を含む
※2:多胎妊娠の場合にあっては、14週間
・申請方法:ダイナムネットからワークフローにて起票
≪ワークフロー⇒新規申請⇒就業関連⇒深夜業務制限請求書⇒本人申請≫
≪ワークフロー⇒新規申請⇒就業関連⇒時間外労働制限請求書⇒本人申請≫
小学校6年生までの子どもの負傷・疾病の世話を行なうためまたは予防接種や健康診断を受けさせるため取得できる無給の休暇が看護休暇となります。4月1日から翌年3月31日の間で、
対象となる子が1人の場合は年5日以内
対象となる子が2人以上の場合は年10日以内
で取得できます。(同一の子について5日以上取得することも可能)
ただし、勤続6か月未満の方及び所定就業日数3日以下の方は取得する事ができません。
これに限らず特別休暇は基本的に事前の届け出が必要となりますが、やむを得ない事由がある場合には連絡だけは速やかに行なっておき、届け出は翌出勤日でも可能となっています。
・申請方法:ダイナムネットからワークフローにて申請
≪ワークフロー⇒新規申請⇒就業関連⇒休暇申請書⇒本人申請≫
添付書類:子の看護休暇申出書
※こちらは上記ワークフロー画面でダウンロードが可能です。
組合からのお祝いとして、義務教育の期間(小・中学)入学の際に図書券を3,000円分お届けしています。申請の際には入学を証明できるもの(お子様の健康保険証のコピー)を添付してください。
・申請方法:ダイナムネットからワークフローにて申請
≪ダイナムユニオンホームページ⇒慶弔制度⇒慶事申請書≫
※社内文書からもダウンロード可能です。
育児休業給付金には・・・
基本給付金…休業開始前6カ月の平均給与×30%×育休月数
職場復帰給付金…休業開始前6カ月の平均給与×20%×育休月数
上記の給付金は雇用保険から支給されるので雇用保険に加入し、休業前の2年間に1カ月に11日以上働いた付きが12カ月以上あることが条件です。必要書類についてはダイナム情報処理から育児休暇に入った事が確認でき次第送付されます。
※2010年(平成22年)4月に制度が改正され、2010年4月以降に育児休業を取得した場合は「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が統合され「育児休業給付金」として全額育児休業中に支給されることになりました。支給額は休業開始時賃金の40%ですが、暫定措置として制度開始時より当面の間は50%に引き上げられています。
※児童手当金は一定以上の所得がある場合には受給できません。
| 制度 | 規定名 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| (1)育児休業 | 育児休業等に関する規定 | 第2条〜第15条(育児休業) |
| (2)勤務時間の短縮措置 | 育児休業等に関する規定 | 第16条(勤務時間の短縮措置) |
| (3)育児のための深夜業制限 | 育児休業等に関する規定 | 第17条(育児のための深夜業の制限) |
| (4)育児のための時間外労働制限 | 育児休業等に関する規定 | 第18条(育児のための時間外労働の制限) |
| (5)看護休暇 | 就業規則 | 第4章 第5節 第42条(看護休暇) |