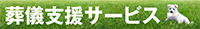■正社員・・・・・・・・基本給の1.78%ただし上限は6,500円(100円未満は切り捨て)※年12回徴収
■勤務地限定社員・・・・・基本給の1.6%ただし上限は3,800円(100円未満は切り捨て)※年12回徴収
■クルー社員・・・・・・[クルー基本給(時間給×労働時間) + 特定日出勤手当含む]の1.50%
ただし上限は1,900円(100円未満は切り捨て)※年12回徴収

第8期(2010年度~2012年度)から、将来的に組合費を引き下げていく方向で検討を進めてきました。
現執行部としては、組合活動もある種「サービス業」であると考えておりますので、「質の高いサービスを安価で」と考えています。
組合員の皆様からは、「組合費が余っている状態」についてご意見を頂くことが多く、そこについて改善をしようと進めてきました。
震災の影響があり、実質的には2012年度から中央執行委員会で組合費の方向性について議論を始めましたが、当時、組合費を引き下げるにはいくつかのハードルがありました。それを一つずつ整理してきた経緯があります。
(震災のあった2011年度には、2010年度剰余金を用いて「災害対策基金」を設立しました。)
2010年度以前は、収入に対して支出がショートする状態が続いてきており、いわゆる「剰余金(=余ったお金)」については「罷業資金(=ストライキ資金)」に積み立ててきたという背景がありました。
組合費の引き下げを検討するにあたり、この「罷業資金」をどのように考えるかは、切っても切り離せないものでした。
1. 2012年度・・・個人旅行補助制度の整理
まず2012年度には、上記「罷業資金」も大きな課題ではありましたが、「旅行補助制度」の整理から手を付けました。
この制度が当時もっとも「支出が読めない」ものでして、毎年実績に合わせて予算を上積みしてきた歴史がありました。これでは組合費は下げられません。
(ちなみに、組合員全員が年間一回利用した場合、総額で6億円以上かかる制度でしたので、発足時すでに成り立っていなかったとも言えるかもしれません。)
制度の整理として、まずは利用回数に制限をかけました。(それまでは利用回数無制限でした)
そしてそれと同時に、翌期、旅行補助制度に代わる福利厚生制度に切り替えるべく事前準備を進めてきました。
2. 2013年度・・・定額のベネフィット・ステーションに切り替え
2013年度には、「旅行補助制度」の打ち切りを決定し(2013年12月末まで)、定額(一人あたり月額80円)の「ベネフィット・ステーション」に切り替えました(2014年1月から)。
※「ベネ」についてはサービス内容に不満を感じている組合員も多く、改善しなければなりません。なお、中には「旅行制度に戻してほしい」という声もありますが、上記の事情からそれは検討していません。
3. 2014年度・・・慶弔特別会計のテコ入れ
2014年度には、「慶弔特別会計」のテコ入れを実施しました。
この特別会計は、組合員の慶事(結婚・出産・入学)や弔事(死亡・傷病・災害)に際してのお祝いやお見舞いを運用している会計ですが、過去は資金不足で2年~3年に一度、一般会計からの繰入金を必要としている状況でした。不定期で一般会計からの繰入金が必要になりますので、要は「支出が読めない」ものの1つとなっていました。
それまでの慶弔会計の収入は、各組合費から150円を切り出して慶弔会計の収入としておりましたが、それを「230円」に見直しました。
※今期(2015年度)1年回した結果、慶弔特別会計は「自走できる会計になった」と判断しております。
4. 2015年度・・・罷業資金の予算化
2015年度には、「罷業資金」の予算化に着手しました。
それまでの罷業資金は、上述の通り「余ったら積み立てる」ものとなっていましたが、そもそも罷業についてどのように考えるかから議論をしました。
結論としては、「組合として罷業の準備は必要であり、意思のある積み立てをするべきである。
「余ったら積み立てる」ということは逆に言うと「余らなければ積み立てない」を意味し、最も意思の無いものである。
よって、必要額(=必要罷業日数)を設定し、それに沿った予算化をするべきである。また、必要罷業日数の判断は、その時代毎の労使関係等に依るため毎年の議論が必要である。」と結論付けました。
これに基づき、現執行部としては、「現状の罷業可能日数(=4日)を維持する積立てが必要」と判断し、それを予算化しました。
(詳細は「罷業の考え方」をご参照下さい)
上記1~4を経て、現在に至ります。
その上で、2015年度予算において約800万円の予備費を確保し、2016年度予算においても約1500万円の予備費を確保できています。
つまり、「真に余った分」が見えるようになってきました。
何年で判断するのが正しいかは別として、このような状況が続くのであれば、それは「削減可能な原資である」と言えると思います。
※厳密に言うと、予算の中であと2つ課題が残っています。
「賃金補償費(出勤扱いで組合活動に参加した場合の賃金補償)」と「職場分会費」です。この2つは毎年実績ベースで予算を組んでいますので、(大きく変動することはあまり考えられませんが)読み切れない支出であるとも言えます。
この点をどうするかも議論が必要です。
執行部としては、ようやくここまできたという感じです。
2017年度の予算では、直接的な議論をしたいと考えています。
引き下げなのか免除なのか、引き下げにしても一律なのか、上限なのか、階層別なのか、もしくは引き下げ分の原資を他へ配分するのか、やり方はいくつかありそうです。
最後に、
これまで組合費に関するご意見は多数頂戴していたものの、執行部としての考え方(姿勢)を明確に発信することが少なかったと反省しております。
現執行部の考え方をご一読頂き、きっと、「そんなふうに考えていたのか。」とご理解頂ける部分もあったかと思います。
今後もなるべく「執行部としての考え方(姿勢)」については、組合員の皆さんに明確に発信していこうと思います。
皆さまのご意見をお待ちしております。
2015年10月7日
中央執行委員長 佐藤 瑞樹
まず、既にご存知かもしれませんが、「そもそも罷業(ストライキ)とは何か?」について説明させて下さい。
罷業とは、労働者によって結成された労働組合が「働く事を拒否する」事によって会社(雇用者)に対して、要求に対する交渉を有利に進めようとすること です。
また、一口に要求と言っても、正当な要求でなければなりませんし、要求の社会的妥当性も問われます。
(※正当な要求とは、労働条件に直接関係するもの(例えば賃金・休暇・労働時間など)のことです。)
次に、「どのような時に実施するのか?」ですが、これは上記の通り組合からの要求と会社の回答に折り合いがつかなかった場合です。
厳密に言いますと、このような場合に、罷業をする可能性があります。
敢えて「可能性がある」とだけ書いたのは、罷業というものが、される側(会社)にとってダメージがあるだけではなく、する側(組合員)にも回りまわってダメージがあるかもしれない性質であるためだからです。
例えば、罷業によるブランドイメージの失墜は、その後のお客様動向にも影響をするかもしれませんし、それによって会社業績が下降し、私たちの処遇にも影響を与え兼ねないからということです。
ですので、罷業というものは「諸刃の剣」と表現されることもあり、罷業の準備は常にしておくべきではありますが、その発動については極めて慎重であるべきという、ある意味矛盾したバランスの中に存在するものです。
罷業の準備の必要性については、その時代その時代の労使関係等を鑑み、時代毎に執行部が判断をします。
現執行部としては、現行の罷業可能日数は約4日分ですが、これを直ちに10日分を目指すとか、1ヶ月分を目指す必要はないと判断しました。
ですが、将来においてもずっとそうかとは言い切れません。ですので、いつまた罷業可能日数を引き上げる必要性にかられたにしても対応できるよう、現行の4日分を維持するだけの罷業資金の予算立ては必要であると結論付けました。
以上が罷業に関する現執行部の考え方です。
尚、これは予備知識ですが、
「実施方法」については、「スト権確立投票」という手順を踏まえることになります。
具体的には、3月の中央委員会の際に、「これから団体交渉に向かうにあたり、最終最後交渉がこじれた際に、罷業という手段をもって交渉に臨んで良いか?」というものを中央委員の皆さんに提案し、賛成/反対を投票して頂く流れになります。
その結果、賛成多数であれば、最終的な手段として罷業という武器をもって団体交渉に臨むことになるというわけです。
2015年10月7日
中央執行委員長 佐藤 瑞樹
2015年3月の中央委員会において、「プールしている組合費の保全」について質問を受けました。
組合費の預け先である中央労働金庫も当然、「※預金保険制度」の対象ではあるものの、万が一の場合にそれによって保護される資産には限りがあります。
万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としているもの。
・預金等の保護の範囲
1、 決済用預金(当座預金、利息のつかない普通預金等)➜全額保護
2、 一般預金等(利息つきの普通預金、定期預金等) ➜合算して元本1,000万円
までとその利息等を保護
※外貨預金、元本補てんのない金銭信託などは対象外
この点について中央執行委員会で議論をしました。
結論としては、現行のまま中央労働金庫に預けることが、最もリスクが低く、最も効率が良い。
ということになりました。
以下、理由を説明します。
まず前提として、
Q➜中央労働金庫に万が一破綻することがあった場合、どうなるか?
A➜1,000万円とその利息分のみ確実に保護され、それを超える部分については破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
※但し、これはどの金融機関に預けていても同じことです。
これは、上記「預金保護制度」による対応であり、
平成14年4月に、それまでの預金等全額保護の特例措置が終了する(いわゆる「ペイオフ解禁」)という流れがあった中で、組合資産の保全について意見・質問があがってきている状況であると推察できます。
組合資産の保全のあり方を検討するにあたり、
ポイントは大きく2点です。
① 万が一の際に、完全に保護される方法はあるのか
② そもそも中央労働金庫に預けることのリスクはどうなのか
①について_____________________________________
中央労働金庫に預けるにせよ、他の金融機関に預けるにせよ、
現在組合が保有する金融資産(約6億円)が完全に保護される形で保有するとなると、
60の金融機関に口座を開き、それぞれ1,000万円ずつ預けることになります。
これは現実的ではありません。
従って、いずれにしてもリスクは0にはなりません。
しかし、「※決済用口座」に切り替えることでリスクを回避することができます。
・無利息
・要求払い(預金者がいつでも払戻しを請求できること)
・決済サービスを提供できること(引き落とし等ができる口座であること)
以上3点を満たすものであり、金融機関が破綻した場合にも全額が保護される。
もちろん、中央労働金庫でも対応が可能である。
但し、この「決済用口座」への切り替えについては、メリットとデメリット両面がある為、
後ほどまた触れますが、
①の結論としては、「決済用口座」の活用という方法があります。
②について_____________________________________
中央労働金庫は他の金融機関(銀行)とは大きく性質が異なる金融機関です。
最も異なる点はその融資先です。一般的な銀行の約65%が企業への融資をしているのに対して、中央労働金庫は99%が個人(組合員)への融資です。
この点で破綻のリスクは既に小さいですが、中央労働金庫の融資の中身の約90%が住宅資金である点も、さらにリスクを小さくしています。
※住宅ローンを組む場合、原則として「団体信用保険」に加入をします。
住宅ローンを組んだ組合員本人に万が一のことがあった場合は、当該保険から借り入れ残額が返済されることになります。
つまり、融資をする金融機関側からすれば、言わば貸し倒れのリスクが極めて低いことになります。
以上を踏まえて、
②の結論としては、中央労働金庫に預けることの方が他金融機関に預けるよりも、よりリスクが小さいと判断しました。
※ここで、先に1で触れた「決済用口座」に関するメリット・デメリットについて検討をします。
「利用配当」とは、取引実績に応じた言わば「還付金」であり、ダイナムユニオンは毎年約65万円ほどを組合費収入に計上できています。
ちなみに、この「利用配当」は中央労働金庫特有のサービスであり、他金融機関には無い大きなメリットであると言えます。
また、万が一のことがあった場合に(ありそうな場合に)、決済用口座に切り替えることも可能である為、そのことからしても、今すぐに配当の無い決済用口座に切り替えるメリットは無いと言えます。
(中央労働金庫の運営状態については定期的に説明を受けており、健全な運営ができているかを執行部でチェックしています。)
以上、①②および決済用口座のメリット・デメリットを総合的勘案し、以下のように判断します。
現行のまま中央労働金庫に預けることが、最もリスクが低く、最も効率が良いと言えます。
※尚、ご意見の中にはMMF等の投信等での積極的な運用を望む声も一部ありますが、いかに安全性が高いとは言え、元本保証が効かない性質の運用である以上、大切な組合費の運用方法としては現執行部では検討しておりません。
2015年10月7日
中央執行委員長 佐藤 瑞樹
≪参考≫
1、ペイオフとは
・ペイオフとは、狭い意味では、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者に保護金を預金保険機構から直接支払う方式のことを指す。
・このほかに、より広い意味で、平成8年6月から講じられてきた預金者等の全額保護の特例措置が終了するということを、「ペイオフ解禁」と呼ぶこともある。
・預金等全額保護(の特例措置)は、平成14年3月末までの時限的な措置であったが、平成17年4月1日から、決済用預金を除くすべての預金について、この特例措置が終了した。
2、組合費口座は全部で6口座あり、使い道によって使い分けをしている。
① 一般会計口座
② 慶弔会計口座
③ 災害対策基金口座
④ 罷業資金口座
⑤ 振り込まれ専用口座
⑥ カンパ用口座
このうち、①②は日常の出し入れがある口座であるため、基本的には大きな金額がプールされている状態ではない。また、⑤⑥は組合員からの振込まれ専用の口座であるため、上記同様に大きな金額がプールされている状態ではない。
組合資産の保全を検討する際には、③と④が関係してくることになる。
3、中央労働金庫の運営状況について(2014年度報告)
・自己資本比率
10.05% 中央労働金庫
16.02% みずほ
15.41% UFJ
17.35% 三井住友
8~15% 地方銀行平均
4.0% 国内基準
・リスク管理債権比率(不良債権比率)
0.78% 中央労働金庫
1.18% みずほ、UFJなど大手平均
2.44% 地方銀行平均